10月22日、タメンタイギャラリーにて「往復書簡 /Correspondance」のVol.1として、WORKSHOP「ヒロシマ わが罪と罰」をよむ、が開催された。広島への原爆投下時に気象観測機のパイロットとして搭乗し、投下の指示を出したクロード・イーザリー。後に広島の人々の幻影に苦しみ、精神を病んだ彼と哲学者ギュンター・アンダースによる著作『ヒロシマわが罪と罰ー原爆パイロットの苦悩の手紙』。二人の間で交わされた往復書簡を、参加者は各自で事前に読み、意見交換を行なった。
参加者:吉田真也、中西あい、岩手萌子、山本功(議事録)、平井亨季(映像記録)
クロード・イーザリー
1918年 – 1978年。アメリカテキサス州出身。太平洋戦争末期の広島原爆投下作戦および長崎原爆投下作戦において、気象観測機(ストレートフラッシュ)のパイロットを勤めた。エノラ・ゲイと共にテニアン基地を発進、広島上空に達した後、爆撃手に対して原爆投下の命令を下した。1947年、空軍から退役。以降、広島の死者の幻影にさいなまれ、銀行強盗などを犯すなど精神に異常をきたし、退役軍人専用の病院に強制収容させられる。アンダースとの文通が行われたのは、この収容中の二年間にあたる。1978年、喉頭癌で死去。
ギュンター・アンダース
1902年 – 1992年。ユダヤ系ドイツ人。ホロコーストや原子力を主題とした思想を展開した。エドムント・フッサールのもとで現象学を学ぶ。1933年、ナチス政権の誕生から逃げるようにパリへと亡命。その後、アメリカに移ったのち、ヨーロッパに戻る。以降、ウィーンに住むようになる。原子力を自らの主要な研究対象とした殆ど唯一の哲学者。体系的な記述に拘らず、自身の体験に引き寄せながら、日常での会話、ふとした断想、時にはフィクションも混ぜながら原子力を論じた独創的な思想を構築した。代表作に、「飢えの行進」、「人間の荒廃」、「橋の上の男」、「核の脅威 原子力時代についての徹底的考察」「異端の思想」などがある。
引き裂かれた英雄像

吉田:まず、僕はこのイーザリーとアンダースという二人の関係性がすごく面白いと感じました。本の中では実際に罪を犯した人のことを下手人というふうに書いてましたけど、この下手人であるイーザリーと、知的な哲学者であるアンダースという、、それこそ映画になってもおかしくないような、二人のキャラクターやそこから生まれるやりとりがドラマとして見ても面白かった。
そこから、原題の「良心の立入禁止区域」というタイトルが示す通り、アンダースという哲学者が自身の知性を武器に、イーザリーという下手人のあまり干渉しにくい感情の領域に入っていく…… それで彼の心を解きほぐすと同時に、世界に対しても問いを投げかけていく。
それから、これは結構本質的な部分でもあると思うんですが、なぜイーザリーが自ら罪を銀行強盗を犯したりとかするようになったのかっていうなことを考えた時に、ロベルト・ユンクの「良心の苦悩」という後書きがあったと思うんですけど、そのある部分が響いたんですね、、ちょっと読みますと、
” その頃、彼の頭の中に少しずつ具体的な形を取り始めていたのはある異常な計画であった。彼は、アメリカの国家的な理想像ともいうべき偉大なる英雄的軍人を、その台座から突き落とし、正体を暴露し、その仮面をひきむくことによって、アメリカ ー に起こってきた、軍人をあがめる新しい風潮に抵抗しようとするのである。そして、彼のこの暴露戦術のまことの対象こそは、他ならぬ彼自身、すなわち” 広島の英雄 ” クロード・ロバート・イーザリー少佐なのである。”
だからイーザリーの目論見というのは、アメリカの英雄像を解体するみたいなことだったと思うんですね。その対象が他ならぬ自分自身であったと。故にそういう方法しか取れなくなって、英雄とそうではない自分との間で、、自分自身を引き裂いた。

中西:私は調べたりしながら読んでたんですが、読めば読むほど混乱していって、、あまりにも自分との間に取っ掛かりがなくて、、まだ感想を言えるほどではないです。なので皆んなからの意見も聞きながら考えたいのですが、、だけど人が困った時に立ち上がる力ってすごいんだなと思って、何かポジティブに前しか見なくなる人間の力。ただそれが、また誰かの力によって違う方向にもいくというか。
吉田:ポジティブな方向にもいくし、場合によってはネガティブな方向にもいく。
アンダースは最初は友人としてイーザリーに寄り添う姿勢で文通を始めたと思うんです。本を見ると、最初はアンダースから手紙が送られ、それにイーザリーが返す形で始まっていて、その一通か二通の段階で既に信頼関係が出来上がっているのがわかります。
岩手:心の友よ、みたいになってた笑
吉田:そうそう。顔も見えてないのに。
だからアンダースはイーザリーを友人としてまずは救おうとした。と同時にこのやりとりを公開することによって、イーザリーの事例を世間に認知させて、世論を変えていこうとした、、それが彼の狙いだったのではないかと僕は思いました。それは結構言葉の端々から伝わってきて、” 残念ながら、これはあなたの問題でもあるが、世界の問題でもある ”みたいなことを言っていたし、、(イーザリーに)友人として接しながらも、研究対象としてもすごく興味深かったんだろうなと、、
それで、だんだんそれが大きな運動に結びついていくのを、、というか二人が結びつけようとしているのを感じました。
機械化していった世界
岩手:イーザリーが、広島に原爆を落とした時は26歳くらいだったと思うけど、(自由と人道とは武力によって守ることができるのだと信じ込み)誠実な心を持って20代からを生きようと思っていた人が、こういう機械のネジのように、どこかで歯車になってしまう、、。(アンダースは原子力時代を機械化する世界、イーザリーのことを機械のネジと例えている)
広島の人に向けた手紙でも(イーザリーは)書いてたけど、広島市を狙わずに、もう少し違う橋の上に落とせば多くの人を殺さずに済むと思っていた、けれど雲が晴れて広島市の中心に落としてしまったと、、一人一人のネジの人たちは、良いことをしようじゃないけど、今よりも希望のある方に向かわせたいと思って色んな行動をとっているけど、それが予期せぬとんでもない事態になってしまうということは、私たちの生活や小さい範囲でもたくさんあると思う。
吉田:自分でも気づかないうちに、流されていったりとか、、
岩手:そうですね。その機械みたいに人間がなっていってるとか、仕組みが機械になっているみたいなことへの警告もあったけど、、それはすごい日々の生活レベルでも思う。何か訳が分かんないことが多すぎるというか。 例えば(川から)水を汲んで水を流したら、手が洗えるとかはすごくわかる。蛇口をひねって、水が出て手を洗うというのもまだ少しわかる。でも自動で(センサー式の蛇口で)水が、ばって出てくるとかは、ちょっと訳が分からなくなってくるというか。。その間が抜かれたりとか、単純化が進んで行く中で、大事な判断も間違ってしまったりとか、それが機械的になっていくことの怖さであり不思議さなんだなって思う。
吉田:今の話、すごく哲学的というか、、面白いですね。
普段そんなに意識しないけど、考えると、何だかわかんなくなってくることってあるじゃないですか。今言ったことはすごい小さい話でしたけど、それがもう少し広がると何か知らないところで大きい物事が進行していたりだとかで、それが不透明でそういうシステムに僕らは気付けない。
広島でも、例えばスタジアムを今まさに建設していますけど、(構想段階から含めて)いつの間にこんなにこんなものが建ったんだとかふと感じる瞬間はあるけど、普段はそれほど疑問には思わない。そのあたりはアンダースの指摘と一致する部分も感じます。ただ時代的なものもあると思っていて、彼が生きていた時代はおそらく機械化、分業化が急速に進んでいった。僕らが生きている時代は、例えばインターネットとか、ヴァーチャルの世界も広がっていてさらに訳が分からなくなってますよね。

岩手:あとは数(手紙の中の「原子力時代の道徳綱領」でアンダースが言及)についても読んだ時に考えて、一人を殺すことは想像できるけど” 10万人という数はもはや想像できない “というのはすごくわかる気がする。ウクライナとかイスラエルの問題とかでも、戦争が勃発したときは、自分の隣人が辛い目にあっているという感覚を覚えたり、日本に居ながらも、住民一人一人のことを思えるんだけど、それが1週間とか1ヶ月経つと自分から離れていくというか、、もっと酷いことになっているはずなのに、どうしようもない気持ちになっていたりとか、無責任な意識になっていたりとかする。
吉田:今の話は、人間の忘却の話題にも繋がるかもしれないですね。人間は忘れないと壊れてしまう。
広島で生きること
吉田:今話してきた機械化する世界とか、個人が気づかないところで物事が進行していくみたいなことを、広島に当てはめて考えてみたいんですが、僕は今広島でイベントの設営であるとか搬入の仕事をしたりするんです。最初は何にもない空間の中に、何十人かで一気に壁を立てたりとか、装飾を施して、フォーマットとかも基本決まっていて1日で出来上がってしまうんですね。そうしてなんとか物産展みたいな感じでお客さんを呼ぶわけですが、その時に何か土地や現実と切り離された一つの世界の中で、人々の欲求を消費させるみたいな、そういう構造を感じます。都市はそもそもそういう性格があるのでしょうけど、広島では結構そういうのを多く感じるんです。(それは原爆が落ちて古い建物があまり残っていないことや、復興ということにもおそらく関係していると思うのですが)と同時に自分の感覚を広げたり、俯瞰しないとそういうことには気付けなかったりします。そうしてそのシステムの中で流され、消費されていく。
ここにいる皆さんは広島で生活している人がほとんどですが、何かそういう違和感みたいなことを感じることはありますか?

岩手:いっぱいあるよ。でもそれが広島なのか日本が全部そうなのかわからない。もう少し人々が考えたりできるような余白のある場所があったらいいのかな。
吉田:余白が欲しいというのは分かる気がします。広島で身振りや思考が規定されてしまう力というか、そういうことを感じることが多いです。そもそも平和記念公園自体が、軸線上に原爆ドームが置かれていたりとか構造的に人々の視線を誘導するようにできていますよね。
今話してる話題にも繋がると思うのですが、ギュンターアンダースは(イーザリーと文通を始める前に)広島に来ていて、その滞在を「橋の上の男」という本の中で書いています。僕がその中ですごく響いた文言があります。少し読むと、
”いや、旅人よ、宮島をやめよ、厳島をやめよ、そして、広島にとどまれ!広島にとどまって、町から町を、橋から橋を、あてどもなくさまようがいい!さまよいながら思いめぐらしてみるがよい。君がさまよっている場所はどこか、君はだれの上を、何の上をさまよっているのかを。さらに思いめぐらしてみるがよい。君が見るもののなかには、もはや真実はないのだということを。そして、君が見るもののなかにはもはや真実はないのだという、ただこれだけが真実であることを。”
アンダースは怒りを露にしながら、かなり強い言葉で批判していて、同時にこの文章の前に、”復興とは破壊の破壊である”という言葉を残しています。一度原爆が落ちて破壊された都市に、また建物が立って街が復興しているように見えるけど、それは死者とか過去の出来事がなかなか想像できないようになってしまっていて、、、つまり復興することによって過去や死者をまた破壊しているということだと思います。それはさっきの余白が生まれにくいとか、そういうことにも関係してくると思いながら、話を聞いてました。
岩手:ただ広島に住む人間としては、そういうこと(復興し、変わっていくこと)を歓迎している部分もあって、宮島であるとか便利な施設であるとか、、ただ同時にそれに対する違和感もあって、ずっと矛盾やジレンマを抱えながら生きているという気持ちがあります。
平和都市での身振り
中西:私は県外から来た身ですけど、住んでみるとやっぱりこれまで触れてこなかった領域に触れざるを得ないっていう感覚があって。別に傷つけたい訳ではないんですが、平和についての催し物が沢山ありますよね。それが誰の何の為のものなのか、何だかよくわからないものになっているというか、自分との間にギャップを感じる時があって、それがさっき話になっていたフォーマット化されたものの中で個が取り扱われてしまうと、そういう感覚に陥るのかなと思いました。
吉田:平和という言葉が叫ばれれば叫ばれるほど、軽薄なものとしてしか認識できなくなってくる。
僕も外から来た身なので、2年ほど住んだ実感としてそういうことを感じます。これまでアーティストとしてはリサーチベースで制作をしていて、土地の可能性みたいなものを探求してきました。ところが広島に来て、本来の土地の可能性みたいなところから切り離されたところで、私たちは生活しているのではというふうに感じ始めて、なんか全てがハリボテに見える瞬間があるんですよね。見えてるものが根に張っていないというか。だから最初は生活が面白くなくて、その面白くなさを批評的に考えていけば逆に意義のあるものができるのではないかと思ったんです。
中西:その話の延長線上でいうと、その時代時代で大多数が受け入れるものに依存した方が楽なんだとも思います。そこに自分もまかれていってるようにも感じます。
吉田:なんかこうシステムの内側で生きていると気付けないことがやっぱりあります。それで僕がさっき言った、街が全てハリボテのように見える瞬間というのは、そういう状態から覚醒して、(そのシステムの)外側の視点を獲得する一歩手前なんじゃないかと思ったりして。じゃあそういう視点をどうすれば会得できるかってなった時に、僕の場合だと身体というものが重要だと思って、お二人と一緒にやりたいと思ったんですね。これは直感的に感じてることかもしれませんが、普段規定されてる身振りや、思想からどう抜け出して覚醒できるかって考えた時に(ダンサー)の身体というものが一役買えるのではと思っています。

パイロットの視点
吉田:この本の象徴的な部分として「広島上空で私がしたこと」というイーザリーから広島のN師にあてた、イーザリー自らの罪や広島上空での体験を告白する箇所があります。この箇所はいくつかの文献で引用されている部分でもあります。(自分のしたことを)後悔する形で告白している部分があるので少し読みます。
”自分の義務を果たすということは第二の素晴らしいことである。そして、この義務とはすなわち、赤、白、黒、あるいは黄色をとわずあらゆる人種の全ての人々に対して、恐怖と貧困と無知と隷属のない、幸福にみちた生活を保障することである —- 私は、広島上空からテニヤンの基地へ帰る飛行機の中で、この義務を果たすことを誓ったのです。これが私の第二の信条なのです。”
イーザリーやその他パイロットの視点は、広島全体を見下ろす上空から俯瞰した視野だと思うんです。優越的にも感じられるし、同時に焼け死んでいる人とか、水を求めて川に入っている人とかそういう細部は見えない。そういう上空から全体を見下ろしている視点は、ある種アメリカ全体の広島への眼差しとも捉えることができるかもしれません。そう考えるとまさにイーザリーの視点はアメリカを代表する視点でもあり、彼個人の視点でもあった。
(この本の中で)イーザリーは後に、焦土と化した広島の写真を見て、自分のしたことを理解したと書かれています。ある意味それは、彼の中で優越的な上空の視点が地上へと段々降りていって、全体から細部へと視点が移っていき、そこで初めて個人の死を理解することができた。そういう考え方もできるかもしれません。個人の視点のうえに全体の視点も背負ってしまったというか、その二重性によって自身が引き裂かれた。そこもアンダースの指摘するプロメテウス的落差(原子力によってもたらされる圧倒的な破壊の現実と貧弱化した想像力との落差)に通じてる気がします。
僕は映像を撮ったりするので、こういう視点について考えてしまうんですが、例えば広島をドローンでとった場合それはどういう意味が出てくるのか。それはどういう視点なのか、そういうことを考えたりします。
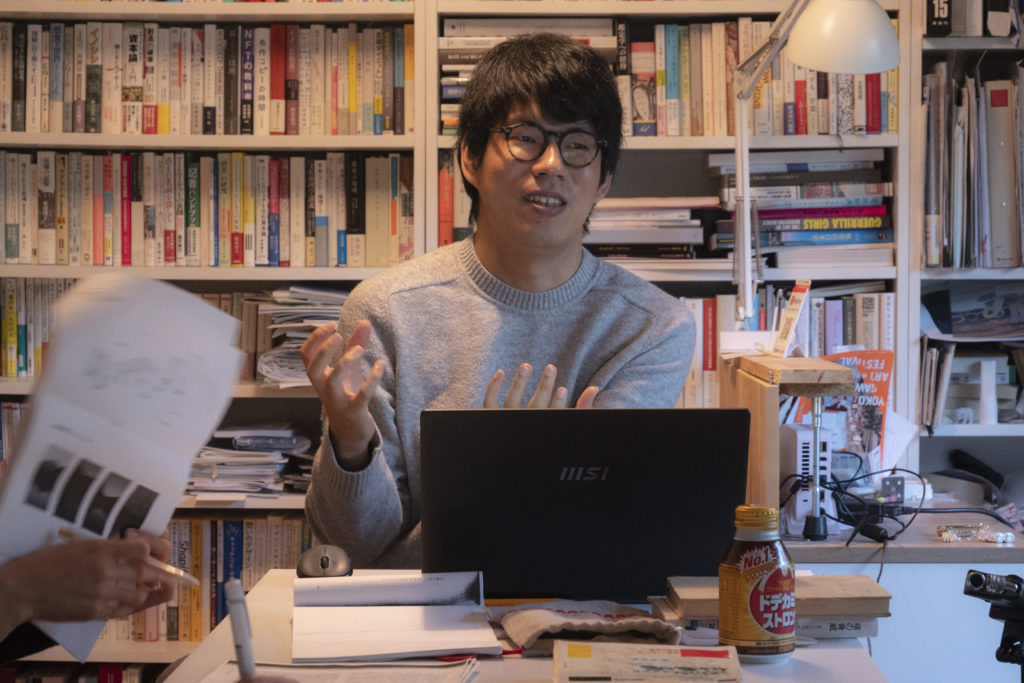
山本:今の話でいうと、原爆投下のイメージって、ピカッ、ドンっていうのと遠くから見えるキノコ雲で、上からの視点って基本あんまり出てこない気がします。それは多分、第二次世界大戦中に日本が飛行機での戦闘をメインにできなかった事もあると思う。知覧の飛行場から飛び立ってとか、神風が突っ込んでいくのを見ている映像が出てくるのが多い気がして、飛んでった人たちが帰ってこなかったとか、映像としてそもそも残っていないというのもあると思うんですが、パイロットの視点はそれほど語られないし、想像できない視点でもあると思います。
吉田:ただ、爆心地から同心円上に、放射能が広がる広島の地図のイメージは、僕らに刷り込まれている気がしますけどね。この流れで、一つ映画の話をしたいのですが、ヴィム・ヴェンダース監督の「ベルリン 天使の詩」という少々難解な映画があります。時代的な背景としては確か撮影されたのは1980年代後半のベルリンで、壁によってまだ東ドイツと西ドイツに分かれていた時でした。それでその映画は天使が主人公で、天使の視点で物語が進んでいくんですね。天使は人々からは見えない設定で、交通事故に遭って今まさに死にゆく男の横で祈ったりとか、サーカスの女の横に座って話を聞いたりとかするんです。当時の政治的な情勢を記録している部分もあるけど、ファンタジックな設定ですごく不思議な映画なんですね。
それですごく印象に残っているシーンがあって、ここからネタバレになっていくんですが笑、、あるとき天使の一人がサーカスの女の子に恋をしてしまって、人間になりたいと言い出すんです。そして確か天空からスーと降っていって、まさにベルリンの壁の境界線上に降り立つんですね。その瞬間モノクロだった映像がカラーに変わります。
それで例えばイーザリーも彼がかつて原爆を落とした広島上空から地上に降りて、死者や広島の人々と話し始めたらどうなるだろうか、という少し変な想像を僕はしてたんです。アンダースも含めて彼らはもう死者ですから、今の広島と対話するとどうなるだろうか、というそういうことを考えてました。
忘却することについて
岩手:アンダース(「橋の上の男」での文言)の話に戻ると、広島の街をさまよえばいいという言葉も、それは広島全てが持ってるから一歩も歩けなくなるというか、どこにも死者は埋まっているし、、それを全て感じながら生きることは人間として無理、、。
山本:それはあなた(アンダース)は他所の人だからというのはちょっと思いますけどね。こっちはその上で生きてるんだよって。住んでる側の忘れたいものとしての過去と、外の人からの、残せ、怒れ、思い出せという対立はある気がします。ただ世代が既に降っていて何を忘れたらいいのか最早わからなくなっている所もあって、、でもなんとなくそれには触れない方が良さそうという空気だけがある。
吉田:当事者の中には、触れたくもない人もいますね。
山本:それもそうだし、(平和祈念式典は)忘れるための祝祭でもある。
吉田:浄化という言葉にも近い気がしますけどね。忘れるということはある反面、決して悪いことではないということですよね。
山本:忘れることは罪なのかという問題提起を(この議論は)孕んでいる気がします。忘れないと人は病んでしまう。
平井:(ここから平井が参加)忘却の話についてですけど、そのことについて語りたくない人と、残そうとする人がいるけど、個人的な感覚では僕の祖父は語りたくない人で、祖母は語る人でした。だけど祖母が祖父のこと、例えばこういう経緯で死なずに済んだとかそういう話をするんですね。だから祖父は、誰かの口が自分の体験を話していたから、自分は話さなかったんだと思って。あるいは自分からは話さないけど、こちらから聞くことをしたら何かを話したかもしれない。
僕らが何かしたら話すとか、ある条件が揃えば語り出すみたいな。誰かと二人だったら話すとか、同じ体験をした人とだったら話すとか、文章だったら書く人もいるかもしれない。そういう(話者と聞き手の)間がたくさんある。
ありがちなのは、話したくない人なんだとこっちから決めつけて、触れてはいけない存在にしてしまうこと。そうすると当たり障りのないことしか言えなくなってしまう。だから重要なのはそこで諦めてしまうのではなく、本当に知りたいのであれば多少悪者になってでも、何らかの手立てを講じることだと思う。そういう意味では、そういう人が住んでいる場所で展覧会を開いて、それを見て話せるようになる人もいると思うんです。だから大きな問題であればあるほど、加害者と被害者みたいに二極化してしまいがちなんだけど、その間を見つけていくのが制作の過程なのではないかと思っています。

吉田:その辺の話は、媒介(メディウム)のはなしにも繋がってくるのかと思いました。表現者が使う表現の形式のことをメディウム(情報を伝えるための媒介の単数)っていうと思うんですけど、例えばダンサーにとってのメディウムは身体と言えるかもしれない。だけど不思議なのは、何かを伝えたかったら直接言えばいいものを、わざわざ僕らはメディウムを通して表現する。例えば平井くんの祖父の場合も、手記に落とし込んだり誰かに話してもらったりと、一度何かをかませているわけですよね。それはやっぱりそうすることで語ることができるようになる、ということがあるんだと思うんです。
演じること、または応答可能性(その不可能性)
平井:日常生活の中でも、直接ではなく何か役を演じることによって伝えるってことがありますよね。例えば、父親が親として子供に話さなくてはいけない時に、一人の人間としては本当は話したくないけど、父親という役を演じることによってそれが可能になる。自分の言葉を何かを介して、情報を伝達している。あとは周りの人が亡くなっていったりして、(過去のことを)伝承していく人が少なくなっていくと、ある人は語り部を演じ始めるということが起きてくる。でもそれは自分の中で何かを介して言葉を伝えている。
吉田:僕も演じるっていうのは可能性があると思っていて、このプロジェクトもある意味イーザリーを広い意味で、(広島で生活している)僕らが演じようとしているんですね。そういう視点に立ったり、加害者みたいな存在を介した時に、これまで語れなかったものが語れるようになるんじゃないかと思うんです。
平井:制作の過程についても、何かを作るってなった時に初めて、図書館にいったり人に話を聞いたりと、知ろうと思えることってあると思うんですね。そういう何かを伝達するための過程で自分の行動が決められていく。そのプロセスやリサーチ自体を面白がっている気はするんですけど、制作者の義務を果たそうとしている感じもある。普段行かないところに足を運んだり、知らない人との関係が生まれたりすると、それ自体が大事なことに思えてくる。そうした過程を整えて展覧会などに繋げていくっていうのが一つの流れとしてあると思うんです。まあなので、情報をどう伝達するかというのは制作そのものにも言えるので、僕らも常々晒されていることでもあります。
山本:役を演じるという話は、責任(responsibility)= 応答可能性という話にも繋がってくる気がします。私に語り得ないことには私には責任がないが、私に語りうることには責任を負うみたいなことの話。その上で過去と現在の広島を結んだ身体表現として、お二人(私たち)がどのように応答できるのか、というのが一つの問いとしてある気がします。その中で僕たちはたまたまこうして出会ったんだけど、如何にしてそこに積極的な意味を見出せるかというのが、このプロジェクトの肝な気がします。
吉田:僕がお二人(中西と岩手)を巻き込んだっていうのはあります笑。
表現か狂気か

山本:さっき話にでた、イーザリーはアメリカの視点を背負わされたみたいな話は僕らにも通じていて、今広島の視点を(私たちが)背負おうとしているとこもあるので、それを如何に病まずにやり切るかっていう、、。責任って聞くと急に重くなるんだけど、如何にレスポンス(応答)できるのかっていうことだと思う。
吉田:広島の原爆について、今(広島に住んでる)僕らが応答する責任があるかというと、ないとも言えるけど、あるとも言える。僕らは過去を遠いものとして認識してるけど、同時に細い糸で繋がっている。
山本:イーザリーは自分の責任の範疇を超えてそれを負ってしまったんだと思います。それはもう繰り返す必要はない。
吉田:イーザリーの場合は、自分の責任とアメリカの責任が一致してしまった。だけど僕らは、世界の出来事と自分の事との間には距離がありますよね。自分の問題と世界の問題が一致してしまうと、やっぱり人間はおかしくなってしまう。だからイーザリーのことを演じるとなったときに、あまりにも憑依させてしまうと自分を見失ってしまう。自分と(他者と)の距離は保たなくてはいけない。
山本:力の使い方の話も少ししたかったんです。一番最初にアンダースが自分の力を使ってイーザリーに介入していったという話があったと思うんです。力をどういう方向に使うべきかとか、何が良くて何が悪いかは時代を経て見ないとわからないんですが、表現の力の使い方もその話に重ね合わせられないかと思いました。つまり表現の力をどのように使って世界の問題に介入していくか。
吉田:それは表現とアクティビズムの結びつきの話ですか?
山本:まぁ、まぁ。アンダースは自分の哲学の力をアクティビズムに結びつけていくっていうやり方をしたんですけど、表現者はその力をどう使えるのかということです。
平井:イーザリーのしたことって、表現とアクティビズムの両面から考えられると思うんです。彼が捕まえられるためにやったことって、表現として考えるとすごいことをしたなって、思います。国家の法では自分のしたこと(原爆投下)は裁けないけど、自分はそのことで罪を感じているから、(別の罪を犯し)国家の法に則って裁かれようとするという。イーザリーって特異な存在で、法とか国家という枠組みを揺るがす存在であるから病院から出されなかった訳ですよね。そこに隔離することによって国の秩序をも守ろうとした。だからトリックスター(神話などに登場する神や自然の秩序を破り、物語を展開する存在)的な存在になり得そうだったけど、そうはさせなかった。そういう見方もできます。
吉田:今、ハッて思ったのは(イーザリーのしたことは)表現やパフォーマンスだったのかもと思いました。
平井:すごいギリギリですよね。表現か狂気か、というところもそうだし、表現かアクティビズムか、というところも。
普通の暮らしをしようとして出来なくて、そういう行動にでたという過程もすごくリアリティがあるし、パフォーマンスとして解釈してみるというのも一個方法としてあるかもしれないですね。あるいはイーザリーをなぞりつつ、彼が出来なかったことや、違う方法を考えてみるのも面白い。
アンダースはイーザリーの経験を、人道的な運動に結びつけていったけど、もう少し身近な、例えば忘却の問題とかそういうものにも繋げられる気がします。イーザリーがした行動を、今丁寧に迂回しながら読み解いていくと、二項対立の構造(アメリカと日本、被害者と加害者)の中で溢れてしまうものをうまく絡め取りながらそういう問題に接続できる気がします。
こういう大きな問題に対して、抽象的な議論は非常に難しい。イーザリーの行為とかその時の状況、あるいは文通の二人の関係性を読んでいって、それに何か類するものをやってみるとか、そういうふうに引き寄せて、広島に落とし込んでいくことが出来そうなことだと思います。
往復書簡/コレスポンダンス
吉田:最後にこのプログラムのタイトルにもなっている、” 往復書簡/Correspondance ”という言葉について触れておきたいのですが、この言葉には大きく二つの意味があります。一つは往復するという意味、もう一つは一致するという意味です。この言葉は元々ラテン語なんですが、ルネサンス期のフランスでも広まっていて、特殊な意味をボードレールが定義しています。彼は万物照応と呼んでいて、西洋のなかなか難しい意味なんですが天と地を結ぶ縦軸が変化すると横軸もそれに合わせて変化するという、万物が呼応し合うみたいな意味なんですね。そういう第三の意味も入ってきます。
それで、これまで話してきた演じることだとか、誰かを介して語るとか、そういう事ともやはりこの往復という言葉は繋がってくる気がします。
平井:例えば自分の中にこれまでとは異なる、イーザリーのような存在を入れてみる。そういう存在と呼応していくことが自分の体の中で起きている往復、通信と言えるかもしれない。全てが自分ではない状態の中で、自分ではない何かと距離を取り合って交わっていく、そういうところに可能性があるのかなと。
吉田:イーザリーのような存在って僕らからしたらすごく遠い存在だと思うんです。そういう存在にまずは歩み寄っていくんだけど、そこから自分たちのところに帰っていく、往復する必要があると思います。そういう他者と出会い直す中で、他者や自分、あるいは過去や現在が二重映しになっていく、その重なりに意義があるのではないかと思っています。



コメント